梅毒がよくわかる疾患ガイドページ
梅毒は、梅毒トレポネーマ(トレポネーマ・パリダム)という細菌によって引き起こされる性感染症です。感染初期には、感染部位に無痛の潰瘍が形成されることが一般的ですが、治療を受けない場合、病気は進行し、皮膚の発疹、器官損傷、さらには神経系の障害を引き起こす可能性があります。性的接触が主な感染経路であるため、適切な予防策としては、安全な性行為が最も効果的です。
本ガイドでは、梅毒の原因、症状の進行、効果的な治療法、予防策について詳しく解説し、患者が感染のリスクを理解し、適切に管理するための情報を提供します。
梅毒(ばいどく)とは?

梅毒は、トレポネーマ・パリダムという細菌によって引き起こされる性感染症です。感染初期には、性器や口の周囲に無痛の潰瘍(シャンクル)が現れることが特徴です。この潰瘍は自然に治癒することが多いですが、治療を行わない場合、病気はさらに進行し、皮膚の発疹、筋肉痛、発熱、脱毛など、多岐にわたる症状を引き起こすことがあります。
梅毒は治療可能な疾患で、主にペニシリンなどの抗生物質を用いて治療されます。初期段階での治療が最も効果的であり、進行すると神経系や心血管系への深刻な影響を及ぼすことがあります。
近年、日本国内では梅毒の患者数が増加しています。特に若い世代の間での感染が報告されており、2020年には約6,000人以上の患者が報告されました。感染リスクの高まりとともに、性教育の重要性や適切な予防策が強調されています。
厚生労働省や国立感染症研究所は、梅毒の早期発見と治療のために、定期的な検査と予防策の啓発を推奨しています。性交渉の際のコンドームの使用や、感染が疑われる場合の迅速な医療機関への相談が、感染拡大を防ぐ鍵とされています。
段階的に進行していく梅毒の症状
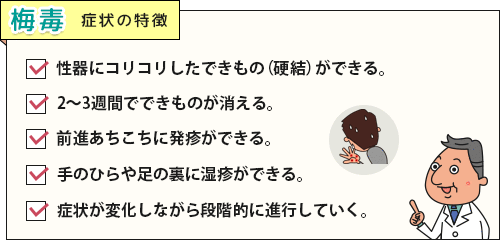
梅毒の症状は、発症と鎮静化を繰り返して第4期まで進行していきます。
現在、第2期には投薬による治療が行われて、第3期以降に進行するケースはほとんどみられていません。時には原因菌が神経に侵入して頭痛や吐き気を発生させることがありますので、主な症状と合わせて確認してください。
第1期(感染後3週~3ヶ月)の症状は硬いしこりやリンパの腫れ。
梅毒トレポネーマに感染すると、3週間の潜伏期間を経て性器に硬いしこりが出現します。これは初期硬結と呼ばれる症状で、コリコリしたしこりが特徴です。
初期硬結は段々と硬さを増していきます。悪化すると中心部がジクジクする潰瘍(硬性下疳)になります。いずれも痛みを伴わないため、発症に気づかないことも多いです。
これらの初期症状は、男性では亀頭や包皮、亀頭溝(カリ首)などに出ます。女性では大陰唇や小陰唇、子宮膣部などに発症します。
硬結などの初期症状の発現からやや遅れて、足の付け根にあるリンパ節に硬い腫れが生じます。このリンパ節の腫れには痛みがありません。大きさは指の先程度であり、複数個見られることが多いです。
第1期の初期症状は2~3週間で消えますが、これは治ったわけではありません。抗生物質で治療しなければ、梅毒トレポネーマは体内に潜伏したままの状態となります。症状が消えた後も放置したままにしていると、第2期フェーズに進行してしまいます。
第2期(感染後3ヶ月~3年)の症状はバラ疹などの多様な発疹。
第1期の発症から約3ヶ月で第2期に進行します。
主に全身の多様な発疹、リンパ節の腫れ、発熱・倦怠感などの症状が出ます。発疹自体に痛みや痒みはありません。症状が発症している期間は人によって異なります。炎症が起こることがあり、頭痛、聴覚や視覚などの障害を引き起こす可能性もあります。
第2期で最初に出る症状は、梅毒性バラ疹と呼ばれる発疹です。うっすらとした紅色の発疹が、手の平や足の裏、全身に多数現れます。バラ疹の大きさは5mm~20mm程度です。放置していると数週間で消えます。バラ疹はあまり目立たないため、症状に気付かずに見過ごされることもあります。
その後、丘疹性梅毒疹というコリコリとした赤褐色の結節(しこり)が、体中あちこちにできます。丘疹性梅毒疹の大きさは5mm~10mm程度です。
手のひらや足の裏に湿疹ができ、ひっかくとポロポロとしたフケみたいなものが落ちるようであれば、梅毒性乾癬の疑いがあります。梅毒性乾癬の発症は、梅毒と診断される決定的なものとなります。
2期の症状はだいたい3ヶ月~3年にわたって続きます。、再び沈静化して無症候性梅毒となります。
第1期と第2期の間は梅毒トレポネーマの感染力が強くなっています。
第3期(感染後3~10年)の症状は皮膚や骨にできるゴム腫など。
最初の感染から3年以上たつと、第3期梅毒に進行します。治療が確立している現代では、第3期梅毒に至ることは非常にまれです。
第3期梅毒ではゴム腫と呼ばれる腫瘍が、皮膚や骨、筋肉など身体中のいたるところに生じます。ゴム腫は柔らかくて弾力があり、エンドウ豆から鶏卵ほどの大きさをしています。ゴム腫は周囲の組織を破壊します。「梅毒にかかると鼻が落ちる」と表現されることがありますが、これはゴム腫によって鼻の骨が陥没した状態です。
第3期にはゴム腫に加えて、赤銅色のしこり(結節性梅毒疹)が顔面に多数発生することもあります。
第4期(感染後10年~)の症状は全身麻痺や認知症など。
感染から10年以上が経過すると、第4期を発症します。様々な臓器に腫瘍が発生したり、心血管系や中枢神経の障害が現れます。梅毒トレポネーマに心血管系を侵されると、大動脈瘤や大動脈炎が生じます。中枢神経を侵されると、全身の麻痺や歩行障害、認知症・記憶障害が生じます。死亡に至るおそれのある、極めて重篤な状態です。ただし第3期と同様に現在ではほとんど見られません。
性交による皮膚や粘膜の小さな傷からの感染が梅毒の原因
梅毒トレポネーマは空気中で長く生きられず、大半は性交により感染します。
細菌は皮膚や粘膜の小さな傷を通って体内に入り、リンパ節を経由して全身に行き渡ります。感染しても免疫ができない性質のため、何度も再感染・発症する可能性があります。
性交の際は妊娠の可能性がなくても必ずコンドームを着用するように心がけましょう。また、多数の相手と性行為を行うことは性病感染リスクを高めます。
梅毒には先天的な感染と後天的な感染があります。上記のような性交による感染は後天的なものです。先天的なものは胎児のときに母親から感染します。現在、先天的な梅毒はほとんど見られなくなりましたが、梅毒に感染した胎児はさまざまな障害を持って生まれてくる確率が高くなります。
梅毒は、フェーズが進行するまで発症に気づきにくい病気です。体に表れる発疹も、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患と見分けがつきにくくなります。他の湿疹と勘違いし、発見が遅れる要因のひとつとなります。体に不調を感じたら早めに検査を受けることが大切です。また、自分の感染が発覚した際は、パートナーにも感染している可能性があります。
梅毒トレポネーマに感染したら早期の発見と治療が重要になります。
梅毒の治療にはペニシリン系抗生物質が有効
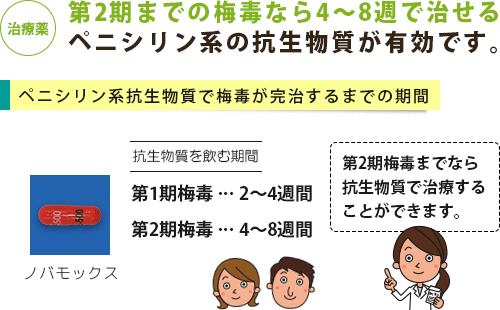
- 梅毒の治療に有効な成分
- アモキシシリン
風邪、膀胱炎の治療に効果的な成分です。病原細菌の細胞壁を壊して殺菌的な働きをします。ペニシリン系の代表的な抗生物質で、梅毒の治療に第一選択されます。
- アモキシシリンが配合されている商品
- ノバモックス
一般的によく使われている抗生物質サワシリンのジェネリックです。梅毒治療の第一選択薬としても用いられ、第1期、第2期の梅毒を1~2ヶ月の服用で治療する効果があります。
梅毒は段階を踏んで悪化していく病気のため、早期発見・早期治療が大切です。
梅毒には、殺菌能力が高くて耐性にも強いペニシリン系抗菌薬が有効です。ペニシリンの摂取方法として点滴注射と内服が選択できます。内服ではアモキシシリンがよく使用されています。
アモキシシリンはインスリン系抗生物質で、細菌の細胞壁を崩して増殖を抑制することで殺菌的な作用を示します。アモキシシリンを有効成分として配合している医薬品としてサワシリンやノバモックスが治療薬として用いられます。
梅毒の治療薬を投与する期間は、進行時期によって異なります。
第1期は2~4週間、第2期は4~8週間、第3期以降が8~12週間です。
無症状の期間に梅毒が発覚した場合は、感染時期を推定して抗生物質を投与します。抗生物質の投与により梅毒トレポネーマが破壊されると、体にさまざまな症状が出る場合があります。倦怠感や発熱、頭痛や血圧の低下などが起こりえます。この症状は24時間以内におさまることが大半です。
神経梅毒の場合は、点滴注射を10日~2週間投与する必要があります。
ペニシリンアレルギーを持つ方への治療は、塩酸ミノサイクリンを、妊婦の方にはアセチルスピラマイシンを使用します。
![[204時間限定] 夏のタイムセール](/template/default/img/campaign/20250723/bn-campaign-a-20250723.webp)