高血圧症がよくわかる疾患ガイドページ
高血圧症は、血圧が常に高い水準を維持する状態を指し、心臓病や脳卒中など、さまざまな健康問題のリスクを高めます。多くの場合、特定の症状が現れにくい「サイレントキラー」とも呼ばれます。不健康な食生活、運動不足、遺伝的要因などが原因となり得ますが、適切な生活習慣の管理と治療によって、血圧をコントロールし健康リスクを減らすことが可能です。
このガイドでは、高血圧症の基礎知識、原因として考えられる要因、潜在的な症状、治療および予防のための実践的なアプローチについて、患者が理解しやすいように説明し、健康的な生活への第一歩を支援します。
高血圧症(こうけつあつしょう)とは?

高血圧症は、血圧が正常値よりも持続的に高い状態を指します。血圧とは、心臓が血液を体中に送り出す際に血管壁にかかる圧力のことで、高血圧症ではこの圧力が常に高めです。高血圧症自体に特有の症状は少ないものの、放置すると心臓病、脳卒中、腎臓病などの重大な健康問題を引き起こすリスクが高まります。
高血圧の原因には、遺伝的要因や食生活(特に塩分の過剰摂取)、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、過度のアルコール摂取などがあります。これらの生活習慣の見直しによって、血圧を下げることが可能です。
日本では、高血圧症は成人の約3人に1人が罹患しているとされ、高齢化に伴い患者数は増加傾向にあります。特に、日本人の食生活における塩分摂取量が高いことが、高血圧症のリスクを高めていると指摘されています。健康診断を通じた早期発見や、適切な治療・管理が推奨されており、医師の指導の下で薬物療法を行う場合もあります。
高血圧症の予防や管理には、バランスの良い食事、定期的な運動、適正な体重の維持、ストレスの軽減、禁煙などが効果的です。また、定期的な血圧測定によって自分の血圧を知り、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。
高血圧症は特徴的な症状が現れない
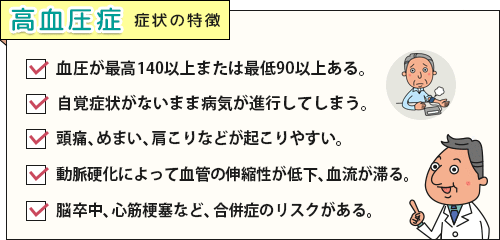
高血圧症では、自覚症状が出現することがほとんどありません。重度になると、頭痛やめまい、肩こりなどが起こりやすくなりますが、特有の症状ではないため、これらの症状が高血圧症を断定する材料にはなりません。体には何の不調も出てないのに健康診断を受けた際に高血圧と指摘されることもよくあります。
症状の有無に関係なく定期的な検査を受けることが高血圧症を予防するうえで大切です。
高血圧症で本当に恐ろしいのは合併症です。症状が出ないからといって、血圧が高い状態を放置して良いわけではありません。血管に負担をかけ続ける高血圧症は、命に関わるような重い合併症の引き金となります。
特徴的な自覚症状が出ないゆえに高血圧症の発見が遅くなり、気づいた頃には合併症を発症していることがあります。合併症の初期症状として、頭痛やめまい、吐き気、疲労感などの症状がみられる場合があります。
血圧値が140/90mmHgを超える状態が続きます。
診察時の血圧値が140/90mmHg以上だと高血圧症と診断されます。気を付けなくてはならないのが、この値はあくまで診察室で測定した際の基準値であるという点です。診察室という特別な環境では、緊張によって普段よりも血圧が高くなる傾向があります。
平常心で測る家庭血圧値では、135/85mmHg以上だと高血圧症と判断できます。
測定装置を24時間身につけて測定する「24時間自由行動下血圧値」では、130/80mmHg以上の場合に高血圧症と判断されます。
動脈硬化によって脳や心臓などの罹患リスクが高くなります。
血圧が高い状態が続くと血管のしなやかさが失われ、次第に伸縮機能が衰えます。血管内部にはコレステロールなどが溜まりやすくなってしまい、血液が流れるスペースが狭くなり、血流が滞るようになります。このような状態を動脈硬化といい、高血圧症をさらに悪化させる要因となります。高血圧症と動脈硬化が互いに促進しあう悪循環が生じるおそれがあります。
動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞、慢性腎臓病などさまざまな合併症の原因となります。特に脳卒中や心疾患などの脳心血管病では、高血圧症は最大の危険因子と考えられており、決して軽視できません。
高血圧症を自覚していて胸の痛みなどの症状があると、狭心症や心筋梗塞の合併が疑われます。めまいや嘔吐、体の一部が麻痺するなどの症状があると、脳障害が懸念されます。むくみなどの症状があれば腎臓に障害が出ている可能性があります。
原因が異なる本態性高血圧症と二次性高血圧症
高血圧症は原因によって「本態性高血圧症」と「二次性高血圧症」に分類されています。
本態性高血圧症は高血圧症の9割程度を占めており、原因として塩分過多や運動不足、加齢による血管の老化、肥満、遺伝などが考えられています。
二次性高血圧症は腎臓疾患や原発性アルドステロン症など特定の原因により発症します。
本態性高血圧症は塩分過多や遺伝が主な原因です。
本態性高血圧症は、実際に血圧の上昇が認められた際に何が原因となっているのか、明確に特定できないのが現状です。日本人に多い本態性高血圧症の原因として塩分の摂り過ぎが考えられます。日本食には、醤油や味噌といった調味料や漬物などの保存食のように塩分が高いものが多くあります。塩分が多い食事を摂り続けていると、血中の塩分濃度が上がり過ぎないように水分で薄めようとする働きから、血管内の血液量が増えて血圧が上昇します。
本態性高血圧症は遺伝因子が罹患しやすさに30〜70%ほど影響するとされており、両親が高血圧症だと子供も高血圧症になりやすいという調査結果が出ています。子供が高血圧症になる素因を有している確率は、両親が高血圧症の場合は1/2、どちらかの親が高血圧症の場合は1/3、両親とも高血圧症でない場合は1/20だと報告されています。
二次性高血圧症の主な原因は腎機能の低下です。
二次性高血圧症の中では、腎実質高血圧や腎血管性高血圧、原発性アルドステロン症などが比較的多いとされています。腎実質高血圧は慢性糸球体腎炎や間質性腎疾患などの腎臓病が原因となります。
慢性腎臓病は50〜70%が二次性高血圧を合併するとされており、腎機能低下が著しいほど合併する頻度が高くなります。腎血管性高血圧は腎動脈の狭窄が原因となって血圧が上昇します。
原発性アルドステロン症は、副腎からアルドステロンというホルモンが過剰に分泌されることで高血圧症となります。
高血圧症の原因「本態性および二次性における血圧上昇の危険因子」
高血圧症は5種類の降圧薬から適切な治療薬を選ぶ
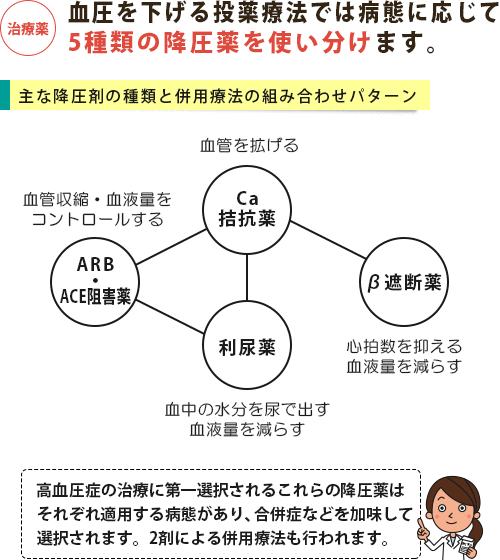
- カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)の有効成分
- アムロジピン
高血圧治療の第一選択薬として用いられるカルシウム拮抗薬で、ゆっくりと効き始め、長時間作用するのが特徴です。血糖や尿酸、脂質などに悪影響を与えません。 - ニフェジピン
血圧を下げる効果が強い特性があり、臓器への血流を保持する働きにも優れた高血圧症・狭心症治療薬です。血管を拡張させる働きによって、血圧の上昇を抑えます。 - 上記の成分が配合されている商品
- ノルバスク
高血圧症の治療に第一選択されているカルシウム(Ca)拮抗薬です。有効成分アムロジピンの働きにより血管の収縮を抑制して血圧を低下させます。 - アダラートCR
有効成分ニフェジピンの効果を長時間持続させるために開発された徐放剤です。2段階に分けて有効成分を放出することで、24時間まで持続時間を延ばすことに成功しています。
- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)の有効成分
- テルミサルタン
血管の収縮を抑制することで降圧効果を示す高血圧症治療剤です。アンジオテンシンII受容体拮抗薬の一種で、比較的副作用が少ないとされています。服用から24時間効果が持続します。 - バルサルタン
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬と呼ばれる高血圧症の治療薬です。1回の服用で24時間効果が持続します。心不全や糖尿病、腎臓疾患などの患者の高血圧治療に適した降圧剤です。 - オルメサルタン
血管を収縮させるアンジオテンシンの働きを阻害する作用で血管拡張を促す受容体拮抗剤です。高血圧症の治療に用いられ、特に本態性高血圧症に対して高い有効性が確認されています。 - ロサルタン
1日1回の服用で降圧効果が24時間持続する降圧剤です。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の一種ですが、尿酸を低下させる作用があり、高尿酸血症を合併している高血圧症の治療に適しています。 - 上記の成分が配合されている商品
- クレサー
効果の持続性に優れた降圧薬であるミカルディスのジェネリックです。有効成分には先発薬と同じテルミサルタンが含有されており、同等の効き目が期待できます。 - バルザー
高血圧症の治療に用いられるジェネリック医薬品です。有効成分バルサルタンがゆるやかに血圧を下げるため、副作用が出づらいという特徴を持ちます。 - ベニテック
過度に上昇した血圧を正常値に近づける働きを持つ有効成分オルメサルタンメドキソミルを含有しています。血圧を下げる作用機序からアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)に分類されている降圧薬です。 - コサート
高血圧症に加えて2型糖尿病性腎症に対する適応も有するニューロタンのジェネリックです。25mg・50mgの2種類の規格があります。
- アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)の有効成分
- ペリンドプリルエルブミン
アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬に分類される高血圧症治療剤です。降圧効果の他に臓器の保護や糖尿病の改善などの付加的な効果があります。 - 上記の成分が配合されている商品
- コバシル
血管を拡張させる効果が24時間にわたって持続する高血圧症の治療薬です。有効成分としてペリンドプリルエルブミンを含有しており、降圧薬の分類としてはACE(アンジオテンシン変換酵素)阻害薬に属しています。
- 利尿薬の有効成分
- スピロノラクトン
抗アルドステロン作用を有するカリウム保持性利尿薬です。カリウムの排泄を抑制するため、カリウム低下に伴う筋力低下や筋肉のけいれんなどの症状をきたしにくい特徴があります。 - 上記の成分が配合されている商品
- アルダクトン
浮腫や高血圧症の治療に用いられるカリウム保持性利尿薬で、抗アルドステロン性利尿・降圧剤とも呼ばれています。
- β遮断薬の有効成分
- ビソプロロールフマル酸塩
心不全や頻脈、狭心症、心筋梗塞後に伴う高血圧症の治療に適した降圧剤です。ノルアドレナリンとβ1受容体の結合を妨げる働きをするβ遮断薬です。 - 上記の成分が配合されている商品
- コンコール
心臓の拍動を抑えることで血圧をコントロールするβ遮断薬に分類される降圧薬です。有効成分のビソプロロールフマル酸塩は、心臓の交感神経に作用して送り出す血液量を減らすことで降圧効果を示します。
| 治療法の内容 | 生活習慣の改善および降圧薬の服用 |
|---|---|
| 診察が行える診療科 | 循環器内科 |
| 施術に使用する薬 | カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬) アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB) アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬) 利尿薬 β遮断薬 |
高血圧症の治療は食事療法や運動療法といった生活習慣の改善から始まり、それでも血圧が下がらない場合に降圧薬による薬物療法が行われます。現在ではさまざまな降圧薬が開発されており、症例に合わせて適した薬を選択することが大切です。単剤で効果が不十分の場合には、用量を増やしたり作用機序の異なる他の降圧薬と併用して治療にあたります。
カルシウム拮抗薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、β遮断薬などの降圧薬が治療に用いられます。
高血圧症の治療に使われる降圧薬は、カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)、β遮断薬、利尿薬の5種が主要となっています。
基本的にはβ遮断薬以外のいずれかが第一選択とされますが、合併症の有無などによって複数の薬を組み合わせたり、使用する薬を変更しながら治療が行われます。
カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)
Ca拮抗薬は左室肥大や狭心症などを併発している方に適しています。
血管を拡げる作用から高血圧症治療に広く用いられていますが、脈が遅くなる徐脈性不整脈の方は使用できません。
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)/アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)
ARBおよびACE阻害薬は、血管の収縮や血液量を増やす作用があるアンジオテンシンⅡという生理活性物質を阻害します。
慢性腎臓病や糖尿病を併発している高血圧症の治療に多く利用されています。妊婦や高カリウム血症を患っている方への使用は禁忌です。
利尿薬
利尿薬は血中の水分を尿として排出することで血液量を減らし、血圧を改善させます。
心不全や骨粗しょう症などを伴うケースには積極的に使用されます。対して、低カリウム血症を患っている方の高血圧治療には適していません。
β遮断薬
β遮断薬は心臓の動きを穏やかにして心拍数を適度に減らします。全身に送り出される血液量が低下するため、高血圧の改善に有効です。
頻脈や心筋梗塞後の高血圧症には効果的に作用する一方で、喘息や高度の徐脈性不整脈の方は使用できません。
高血圧症の予防は偏った食事と運動不足の改善から
- 食生活の改善(減塩、ミネラル類の摂取など)
- 運動不足の改善
- 節酒、節煙
血圧の上昇を予防するためには、生活習慣の見直しが重要です。高血圧の主な要因は栄養バランスの偏った食事や運動不足など生活習慣の乱れにあります。これらを解消することで血圧上昇の抑制や予防が期待できます。
食生活において真っ先に気にするべきは塩分の摂取量です。目標としては一日の塩分摂取量を6mg未満に抑えると良いとされていますが、より少なくすることが理想です。また、マグネシウムやカルシウムなどのミネラル類は塩分の排出を助ける働きがあるので積極的に摂取しましょう。
適度な有酸素運動により降圧効果が得られます。ややきついと感じるくらいの運動が丁度良く、ウォーキングやサイクリングなどが適しています。運動すると、交感神経の働きの減弱、インスリンの働きが良くなる、利尿作用が活発になるといった作用から血圧が下がります。
アルコールの飲み過ぎや喫煙は血圧の上昇を引き起こします。アルコールは少量であれば血流を良くして降圧する効果がありますが、飲み過ぎると血圧を上げることが指摘されています。タバコは血圧の上昇だけでなく動脈硬化を促進する原因でもあります。血圧が高めの方はタバコの本数を減らし、可能であれば禁煙してください。
