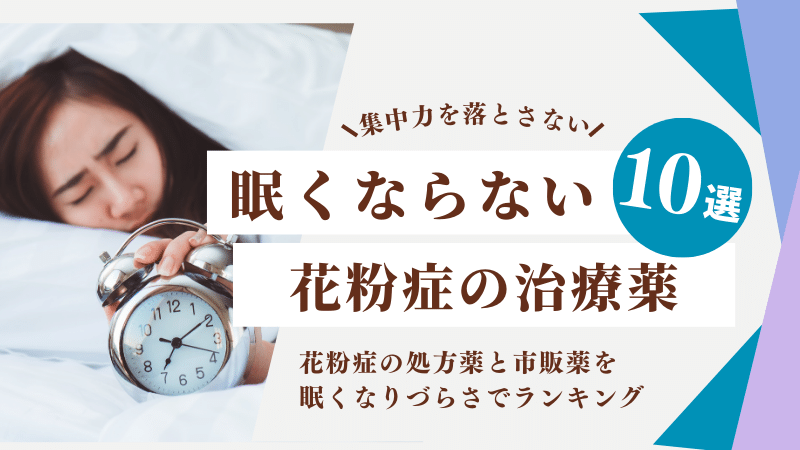ルパフィンの副作用「眠気はいつまで?他の薬との比較」について
ルパフィンは、花粉症やアレルギー性鼻炎、蕁麻疹の治療に使用される抗ヒスタミン薬で、その有効成分ルパタジンによりアレルギー症状の緩和を図ります。
本記事では、ルパフィンの使用における副作用に焦点を当て、特に頻度の高い眠気をはじめ、口渇や倦怠感などの副作用や、より稀ではあるが重大な副作用についても解説します。
ルパフィンの服用は、これらの副作用を十分に理解した上で、適切なタイミングで行うことが推奨されます。また、服用後は自動車の運転など、注意力を要する活動を避けるべきであり、副作用が現れた場合には速やかに医師の診断を受けることが重要です。
ルパフィンの主な副作用は眠気
ルパフィンの発売前に行われた臨床試験では、特に発症頻度が高い副作用として以下が報告されています。
| 副作用 | 発現率 |
|---|---|
| 眠気 | 9.3% |
| 口渇 | 0.7% |
| 倦怠感 | 0.6% |
| ALT(GPT)上昇 | 0.5% |
| AST(GOT)上昇 | 0.5% |
| 尿糖 | 0.4% |
| 尿蛋白 | 0.4% |
※「AST上昇」や「ALT上昇」は肝臓機能の異常を示しており、「尿糖」や「尿蛋白」は血糖値や腎臓の異常を示しています。
中でも高い頻度で確認されているのが「眠気」の副作用です。2番目に多い「口渇」と比べても10倍以上の頻度で確認されています。
眠気は、ルパフィンの有効成分が脳に入り込むことでおきる副作用です。思考力や集中力が低下して、眠いと感じることがあります。
3番目に高い頻度で報告されている「倦怠感」も、同様の理由で生じていることが考えられます。
日中に眠気や倦怠感が生じるのを避けるためにも、ルパフィンを服用するタイミングは就寝前に設定するのがおすすめです。
- ルパフィンの副作用の発現頻度についての参考サイト
- IF_ルパフィン錠10mg - 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PDF:4.34 MB)
自動車の運転が禁止されている
眠気が生じる可能性が高いルパフィンは、服用後に自動車の運転を行うことが禁止されています。
実際にルパフィンの添付文書には、以下のような記載があります。
眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること
添付文書 :ルパフィン錠10mg(2022年06月07日)
自動車の運転中に急な眠気におそわれると、重大な事故やケガに繋がるおそれがあるため、こういった注意喚起がされているのです。
一方、ルパフィン以外の抗ヒスタミン薬の中には、自動車の運転に関する規制がない製品(アレグラなど)もあります。
自動車の運転に関する規制がない薬は、発売前に行われた自動車の運転能力テストで安全性が認められています。
日常的に自動車の運転を行う予定のある方は、眠気がおこりづらい別の抗ヒスタミン薬を選ぶようにしましょう。
眠気の強さを他の抗ヒスタミン薬と比較

旧来の抗ヒスタミン薬と比べれば改善されているとはいえ、最新(第二世代)の抗ヒスタミン薬で比べると、ルパフィンは比較的眠気が出やすい薬といえます。
先述した通り、ルパフィンは自動車運転に関する安全性が認められていません。
また自動車運転が禁止されている薬の中でも、比較的高い頻度で眠気の発現が認められています。
以下は、ルパフィンと同様に自動車の運転が禁止されているアレロック・ジルテック・ザイザルで、各添付文書に記載されている眠気の発現頻度を比べたものです。
| 薬剤 | 眠気の発現率 |
|---|---|
| ルパフィン | 5%以上(9.3%) |
| アレロック | 5%以上 |
| ジルテック | 0.1%〜5%未満 |
| ザイザル | 0.1%〜5%未満 |
上記した値は、薬を直接比較したものではないので、一概に眠気の強さの優劣を示しているわけではありません。
とはいえ、ルパフィンとアレロックでは明らかに他の薬よりも高い頻度を示す表現が使われていることが分かります。
以下の記事では、眠くなりづらい花粉症の薬のランキングを紹介しています。添付文書や論文といった複数のデータから比較しているため、ルパフィンの眠くなりやすさをもっと詳しく知りたい方は参考にしてください。
眠気の副作用はいつまで続く?
ルパフィンの服用後、眠気がどのくらい続くのかははっきりと分かっていません。しかし、有効成分の血中濃度が低下するにしたがって副作用は弱まっていく可能性があります。
一般的に、薬の副作用は有効成分の血中濃度の推移と比例関係にあると考えられています。
ルパフィンの血中濃度は、1時間ほどで最高値に達したのち、20時間ほどかけてゆるやかに低下していきます。
そのため、眠気の副作用は、服用から1時間前後に生じやすく、長くても1日の間に消退していくものと考えられます。
ごくまれに見られる重大な副作用
ルパフィンの副作用は、ほとんどが軽い症状ばかりで重い症状はまず起こりません。
しかし、ごくまれではありますが下記のような重大な副作用が見られることがあるので注意してください。
- ショック、アナフィラキシー
- てんかん
- 痙攣
- 肝機能障害、黄疸
ショック、アナフィラキシー
ショック、アナフィラキシーは、アレルギー反応の中でも特に重大な状態を表します。
体内にアレルゲンが侵入することで皮膚・呼吸器・消化器・循環器・神経などの複数の臓器にアレルギー症状が現れます。
もしショック、アナフィラキシーの疑いがあるような症状が突然かつ複数出現した場合には、すぐに医療機関を受診する必要があります。
めまい、目がうつろになる、呼吸困難、冷や汗、顔面蒼白、体の震え、血圧低下、強い不安感、チクチクした刺激感など
てんかん
てんかんは「てんかん発作」を繰り返す病気です。
てんかん発作には、光がチカチカする、手がピクピク動くなどの比較的軽い症状があれば、突然意識を失って反応がなくなることもあります。
前兆として手足の感覚や視覚、聴覚などに異常が見られることがあります。また、味覚や嗅覚の異常やめまい、吐き気などが出現することもあります。
前兆症状は人によってさまざまですが、その人の前兆症状はいつも同じであることが多いです。
手足がピリピリする、感覚がなくなる、電気が走るような感じがする、手足が熱い・冷たい、点や円形などのいろいろな形や色が見える、視界がぼやける・ゆがむ・一部が見えなくなる、機械の音や人の声が聞こえるなど
痙攣
痙攣とは、筋肉が自分の意志とは関係なく収縮する発作です。手足を硬直させたり、ガタガタと屈伸を繰り返したりします。顔の筋肉がぴくぴくと動いたり、白目になることもあります。
痙攣が起きても数分から数十分で自然に治ることが多いですが、痙攣が起きたらすぐに医師の診察を受けてください。
発作を起こす前に以下のような前兆症状が見られることがあります。
めまい、ふるえ、手足のしびれ、ふらつき、一時的に気が遠のく、手足のぴくつきなど
肝機能障害、黄疸
肝機能障害は、肝機能が著しく低下している状態です。初期症状がほとんどなく、ある程度症状が進行すると、全身の倦怠感や食欲の低下、嘔吐、皮膚のかゆみ、体のむくみなどが現れるようになります。
黄疸は、ビリルビンという黄色い色素が代謝できなくなることで目や皮膚が黄色くなってしまう症状です。主に肝機能の低下によって引き起こされます。
黄疸と一緒に腹痛や発熱、皮膚のかゆみ、倦怠感などの症状が出ることもあります。
だるい、食欲不振、吐き気、発熱、発疹、かゆみ、皮膚や白目が黄色くなる、尿が茶褐色など
「めまい」「胃痛」「食欲亢進」などその他の副作用
眠気ほどではありませんが、めまいや胃痛、食欲亢進などもルパフィンの副作用として報告されています。
臨床試験において確認された副作用の発症頻度は、眠気(9.3%)、口渇(0.7%)、倦怠感(0.6%)であり、その他の副作用は0.5%未満でした。
口渇や腹痛、食欲亢進などの胃腸障害に関する副作用
ルパフィンの副作用として、口渇や便秘、腹部不快感、下痢などの胃腸障害を起こすことがあります。
眠気の副作用と比較すると胃腸症状の発症頻度は少ないですが、さまざまな症状が報告されているのでチェックしておきましょう。
- 0.1~5%未満
- 口渇(0.7%)、便秘(0.2%)
- 0.1%未満
- 腹部不快感(0.1%)、下痢(0.1%)、口内乾燥(0.1%)
- 発症頻度不明
- 悪心、嘔吐、消化不良、腹痛、食欲亢進
口渇(こうかつ)は、臨床試験では眠気の次に発症頻度が高いルパフィンの副作用です。
口渇とは、口の中や喉がかわいて水分を欲するようになる状態を指します。薬の副作用以外では、多尿症や脱水症状などに伴うことがあります。
口渇を治すには多量の水を飲む必要があります。口内乾燥であれば、口の中を湿らす程度の水で改善できます。
その他の胃腸障害は、口渇よりも発症頻度が低く、ほとんどが0.1%未満の症状ばかりです。
まれに起こる食欲亢進(しょくよくこうしん)とは、食べたいという欲求が高まることを指します。
ルパフィンを服用してから食事の量が増えた場合は、副作用で食欲が亢進されている可能性があります。
めまいや倦怠感、頭痛などの精神神経に関する副作用
めまいや倦怠感、頭痛などの副作用は、精神神経系に分類されます。比較的発症頻度が高い眠気も精神神経系の副作用です。
それぞれの発症頻度は、他の副作用と一緒に臨床試験によって確認されています。
- 5%以上
- 眠気(9.3%)
- 0.1~5%未満
- 倦怠感(0.6%)
- 0.1%未満
- 頭痛(0.1%)、しびれ感(0.1%)、めまい(0.1%)
- 頻度不明
- 注意力障害、疲労、無力症、易刺激性
精神神経系の副作用の中で比較的発症頻度が高いのは倦怠感です。「身体がだるい」「疲れている」と感じる状態が続くようであれば副作用の可能性があります。
発症頻度は不明ながら易刺激性(いしげきせい)が確認されています。易刺激性とは、ささいなことで不機嫌になったりイライラするようになることです。
めまいや注意力障害などの副作用は、眠気と同様にシチュエーションによっては事故やけがに繋がってしまうことがあります。
しかし、発症頻度から分かるようにこれらの副作用が出現することはほとんどありません。基本的には、眠気にだけ注意していれば問題なくルパフィンを使用できます。
ルパフィンの副作用まとめ
ルパフィンの副作用として最も一般的なのは眠気であり、これはルパフィンの服用者の約9.3%に影響を及ぼします。他にも口渇や倦怠感といった軽度の副作用が報告されていますが、服用後の自動車運転などは厳に慎むべきです。
また、非常に稀ですが、ショックやアナフィラキシー、てんかん、痙攣、肝機能障害、黄疸といった重大な副作用の可能性もあります。これらの重大な副作用はまれに見られるものの、発生した場合は生命を脅かすこともあるため、副作用の初期症状に気付いたら直ちに医療機関を訪れることが求められます。
ルパフィンを安全に使用するためには、これらの副作用を理解し、発生した際には適切な対応を取ることが重要です。