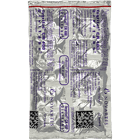カルバマゼピンが配合されている通販商品
カルバマゼピンの禁忌事項
下記に該当する方はカルバマゼピンを使用しないでください。
- カルバマゼピンまたは三環系抗うつ薬に対して過敏症を起こしたことがある
- 重篤な血液障害
- 第Ⅱ度以上の房室ブロック、高度の徐脈(50拍/分未満)
- ポルフィリン症
過去にカルバマゼピンを使用して過敏症を起こしたことがある方は禁忌とされています。化学構造が類似している三環系抗うつ薬で過敏症がでた方も同様です。
血液障害の副作用が報告されているカルバマゼピンでは、重篤な血液障害のある方の使用が禁止されています。もともと重篤な血液障害を抱えている方に副作用の発現が重なった場合、さらに重大な状態に転帰するおそれがあります。
カルバマゼピンは心筋細胞のナトリウムチャネルを阻害して刺激伝導を抑制します。房室ブロックなどの伝導障害のある患者がアダムス・ストークス発作や著しい徐脈を起こした例があるため、これらの患者はカルバマゼピンの使用が禁じられています。
酵素誘導作用があるカルバマゼピンでは、肝臓におけるポリフィリンの合成が促進されます。ポリフィリン症が悪化する可能性があるため、ポリフィリン症患者にカルバマゼピンは禁忌となっております。
カルバマゼピンは下記の薬と併用できません。
- ポリコナゾール(ブイフェンド)
- タダラフィル(アドシルカ)
- リルピビリン(エジュラント)
ポリコナゾールやタダラフィル、リルピビリンはいずれもCYP3Aという酵素の働きで代謝される薬剤です。カルバマゼピンはCYP3Aの誘導作用を有しており、上記の薬剤の代謝を促進して薬効を弱くしてしまうおそれがあることから併用禁忌とされています。ポリコナゾールは真菌症、タダラフィルは肺高血圧症や勃起不全、リルピビリンはHIVの治療に使われる薬です。
カルバマゼピンの働きと効果
- 効能・効果
- てんかん、躁病、双極性障害、統合失調症、三叉神経痛
- (1) てんかんの発作を緩和します。
(2) 躁状態や統合失調症による興奮状態を緩和します。
(3) 三叉神経痛による痛みを緩和します。
一般名:カルバマゼピン
てんかん、躁病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、三叉神経痛の治療に使われるてんかん・三叉神経痛治療剤です。
カルバマゼピンは、てんかんによる神経の過剰な興奮を抑える働きがあり、抗精神作用性てんかん治療剤および躁状態治療剤として使用されています。精神疾患からくる不安や緊張を鎮めたり、発作的に生じた三叉神経痛の強い痛みを防ぐ効果があります。
てんかんの部分発作および三叉神経痛の薬物療法においてカルバマゼピンは第一選択とされています。
部分発作とは、後頭葉や側頭葉など脳の一部で電気発射が起きる発作のことです。意識ははっきりしているけど視覚や聴覚の異常(光がチカチカ見えたり、音がカンカンと聞こえたり)が起きる単純部分発作や徐々に意識が遠のいていく複雑部分発作にカルバマゼピンは優れた治療効果を示します。
部分発作以外にも、全身の強直や痙攣がおきる強直間代発作や何かをしているときに突然意識がなくなる定型欠神発作などの全般発作にもカルバマゼピンは有効です。
カルバマゼピンは1957年にスイスで合成され、1963年にはスイスとイギリスで発売されました。日本国内においては、1966年に向精神作用性てんかんと三叉神経痛の治療薬として発売され、1990年には躁病・双極性障害の躁状態・統合失調症の興奮状態の治療薬としてもカルバマゼピンが用いられるようになりました。
カルバマゼピンは神経細胞に興奮を伝える物質の流入を防ぎます。
カルバマゼピンは神経細胞のナトリウムチャネルを阻害する作用があります。
神経の興奮伝達にはナトリウムイオン(Na+)、カルシウムイオン(Ca2+)、塩化物イオン(Cl-)などが関係しています。プラスの電荷を帯びたNa+やCa2+は興奮性のシグナルとして、マイナスの電荷を帯びたCl-は抑制性のシグナルとして作用します。
細胞が興奮していない状態では、細胞内の電位はマイナスであり細胞外はプラスになっています。なんらかの刺激を受けたりすることで細胞外のNa+が細胞内に入流すると、電位が逆転して脱分極という状態になります。こういった電位の変化により神経細胞の興奮が起きます。
カルバマゼピンはNa+の通り道であるナトリウムチャネルを阻害することで神経細胞内へのNa+の流入を防ぎます。カルバマゼピンにより過剰な興奮が抑制され、てんかん発作や双極性障害、三叉神経痛に改善効果を示します。
臨床試験からてんかんや三叉神経痛などに対する有効性が確かめられています。
| 症例数 | 発作消失 | 改善以上 | ||
|---|---|---|---|---|
| 部分 発作 |
単純部分発作(累積) | 12(100%) | 7(58.3%) | 8(66.7%) |
| 複雑部分発作(累積) | 30(100%) | 15(50.0%) | 21(70.0%) | |
| 二次性全般化発作(累積) | 17(100%) | 11(64.7%) | 14(82.4%) | |
| 全般 発作 |
強直間発作 | 3 | 1 | 2 |
| 強直発作 | 5 | 1 | 3 | |
| 欠神発作 | 1 | 0 | 1 | |
| ミオクロニー | 3 | 2 | 3 | |
| 脱力間代発作 | 1 | 0 | 0 | |
臨床試験*においてカルバマゼピンのてんかん発作に対する有効性が示されています。
てんかんに対する臨床試験では、カルバマゼピン100〜1000mgの服用を3〜18週間続けました。結果として、カルバマゼピンはてんかんの全身発作および部分発作に対して高い改善効果を発揮することや部分発作において6〜8割の改善率を有していることが実証されました。
| 症例数 | 著明改善 | 中等度改善以上 | 軽度改善以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 内因性躁病(累積) | 105(100%) | 42(40.0%) | 72(68.6%) | 88(83.8%) |
| 統合失調症(累積) | 77(100%) | 13(16.9%) | 43(55.8%) | 60(77.9%) |
気分の高揚や興奮状態がみられる躁病や統合失調症に対してもカルバマゼピンは改善効果があります。臨床試験において内因性躁病の患者には1日100~1800mg、統合失調症患者には1日100~1200mgのカルバマゼピンを4~24週間投与したところ、大多数の患者に症状の改善がみられたと報告されています。
| 症例数 | 著効 | 有効以上 | やや有効以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 三叉神経痛(累積) | 35(100%) | 17(48.6%) | 27(77.1%) | 30(85.7%) |
三叉神経痛へのカルバマゼピンの有効性を調べた臨床試験では、35名の三叉神経痛患者にカルバマゼピンを1〜85日間にわたって1日200〜1200mg投与しました。35名のうち30名に症状の改善がみられたことから、カルバマゼピンは三叉神経痛の治療に有効であることが認められました。
※出典:リンク先、販売名:テグレトール錠100mg/テグレトール錠200mg/テグレトール細粒50%のインタビューフォームを参照
テグレトールを先発薬とした抗てんかん治療薬の有効成分として配合されています。
カルバマゼピンの副作用
副作用
眠気、めまい、ふらつき、倦怠感、脱力感、運動失調、過敏症(発疹)、頭痛、頭重、立ちくらみ、口の渇き、抑うつ、興奮、不随意運動(振戦など)、言語障害、食欲不振、吐き気、嘔吐、便秘、下痢、血圧低下、複視、霧視、発熱などが生じることがあります。
重大な副作用
悪性症候群、うっ血性心不全、肝細胞性肝機能障害、間質性腎炎、間質性肺炎、肝機能障害、急性腎不全、血小板減少症、紅皮症、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、再生不良性貧血、ショック、全身性エリテマトーデス様症状、肝汁うっ滞、中毒性表皮壊死症、スティーブンス・ジョンソン症候群、無顆粒球症、溶血性貧血、急性汎発性発疹性膿疱症。
以下はテグレトール錠のインタビューフォーム*に記載されていた副作用の発現率です。
| 副作用の症状 | 発現数 | 発現率 |
|---|---|---|
| 眠気(傾眠) | 223例 | 13.83% |
| めまい | 146例 | 9.05% |
| ふらつき | 137例 | 8.49% |
| けん怠・易疲労感 | 56例 | 3.47% |
| 運動失調 | 56例 | 3.47% |
| 脱力感 | 50例 | 3.10% |
| 頭重・頭痛 | 43例 | 2.67% |
| たちくらみ | 40例 | 2.48% | 口渇 | 34例 | 2.11% | 悪心 | 29例 | 1.80% | 動揺感 | 29例 | 1.80% |
カルバマゼピンの副作用として多くみられるのは、眠気やめまい、ふらつき、けん怠感、疲労感などです。これらの症状が強く出る場合は、服用量を調節する必要があります。
γ-GTP・Al-P・ALTなど肝機能検査値の異常が副作用として現れることもあります。長期にわたりカルバマゼピンを服用する場合は定期的に検査を受け、異変を見逃さないようにしましょう。
カルバマゼピンは神経細胞の興奮を抑制するという作用上、精神疾患系の副作用が目立ちます。頻度が5%以上の症状ではふらつきや眠気、めまいがあり、0.1%〜5%未満では注意力・集中力・反射運動能力などの低下、立ちくらみ、脱力などがみられます。
カルバマゼピンの副作用が重度となることはめったにありませんが、いくつかの重大な副作用の出現が確認されています。重大な副作用が現れることは極めてまれですが、初期症状に注意して疑わしい副作用が出た場合はすぐに医師による診察を受けてください。
- 使用に注意が必要な人
- <心不全、心筋梗塞などの心疾患または第Ⅰ度の房室ブロックのある患者>
カルバマゼピンが刺激伝導を抑制し心機能を悪化させることがあります。心疾患や房室ブロックが重症化する可能性を考慮して慎重に使用しなくてはなりません。 - <排尿困難または眼圧亢進症のある患者>
カルバマゼピンには軽度の抗コリン作用があります。抗コリン作用のある薬剤では眼圧の上昇や排尿困難を起こすことがあるため、排尿困難や眼圧亢進症のある方は症状の悪化に注意してください。 - <高齢者>
一般的に、高齢者は各種臓器の老化に伴い身体機能が衰えており、薬物反応が強く出やすいと考えられます。副作用のふらつきによる転倒や心刺激伝導障害などに注意しながら使用します。 - <肝障害、腎障害のある患者>
代謝・排泄機能の衰えている患者は血中濃度が上昇しやすく、副作用が現れる可能性が通常よりも高くなります。必要に応じて用量を調節したりなど工夫しましょう。 - <薬物過敏症の患者>
カルバマゼピンにはアレルギー症状の報告があります。薬物過敏症の患者はアレルギー性の副作用が現れやすいと考えられるので、慎重にカルバマゼピンを使用しましょう。 - <甲状腺機能低下症の患者>
カルバマゼピンの投与により甲状腺ホルモンT4(チロキシン)の血中濃度低下が確認されています。甲状腺機能低下症の方は注意して使用してください。
- 併用注意薬
- <カルバマゼピンとの併用で代謝が促進される薬>
抗不安・睡眠導入剤、抗てんかん剤、ブチロフェノン系精神神経用剤、三環系抗うつ剤、精神神経用剤、ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗剤、副腎皮質ホルモン剤、黄体・卵胞ホルモン剤、HIVプロテアーゼ阻害剤など。
カルバマゼピンの肝代謝酵素誘導作用によって薬の代謝が促進されると血中濃度が低下して十分な効果が得られないおそれがあります。抗精神病薬のクエチアピンや抗てんかん薬のクロバザムなどは効果が弱くなる一方で、カルバマゼピンの血中濃度を上昇させることが知られています。 - <カルバマゼピンの代謝を阻害する薬>
フルボキサミン、ベラパミル、ジルチアゼム、シメチジン、オメプラゾール、マクロライド系抗生物質、リトナビル、アゾール系抗真菌剤など。
カルバマゼピンの代謝を阻害する薬と併用すると、血中濃度が急激に上昇するため副作用の発現に注意しなければなりません。 - <相互に代謝を促進する薬>
エファビレンツ、フェニトイン、プリミドン。
カルバマゼピンとの併用により相互に代謝酵素を誘導するため、血中濃度が低下することがあります。フェニトインでは代謝競合が起きてフェニトインの代謝が阻害されて血中濃度が上昇することがあります。- <相互に作用増強のおそれがある薬>
MAO阻害薬、中枢神経抑制剤(ハロペリドール、チオリダジン)。
MAO阻害薬はカルバマゼピンと構造が似ている三環系抗うつ薬との併用で相互作用が報告されており、中枢神経抑制剤は薬効が同様であることから互いに作用が強く出すぎる恐れがあります。- その他にシクロホスファミドやラモトリギンなどの薬剤も併用注意薬に設定されています。カルバマゼピンとの併用に注意が必要な医薬品は多いので、普段飲んでいる薬がある方は医師に相談してからカルバマゼピンを服用するようにしてください。
- <相互に作用増強のおそれがある薬>