尖圭コンジローマがよくわかる疾患ガイドページ
尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の特定の型によって引き起こされる性感染症で、主に性器や肛門周辺にイボのような成長を形成します。この病気は見た目が特徴的で、感染者に心理的な影響を及ぼすことがあります。性的接触が主な感染経路であるため、適切な予防策としては、コンドームの使用やHPVワクチンの接種が効果的です。
このガイドでは、尖圭コンジローマの原因、特徴的な症状、治療オプション、そして感染を予防するための方法について詳しく解説し、患者がこの病気を理解し、適切に対処するための支援を目指します。
尖圭コンジローマ(せんけいこんじろーま)とは?

尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって引き起こされる性感染症の一種です。この病気の最も顕著な特徴は、性器や肛門周囲に現れる小さないぼ状の突起です。これらの突起は、カリフラワーのような形をしており、柔らかく湿った質感があります。色は肌色からピンク、時には褐色を帯びることもあります。
尖圭コンジローマは、直接的な肌と肌の接触、特に性交渉によって広がります。ウイルスに感染してもすぐに症状が出るわけではなく、数週間から数ヶ月の潜伏期間を経て初めて症状が現れることが一般的です。
治療方法としては、冷凍療法、レーザー治療、外用薬(イミキモドクリームなど)がありますが、ウイルス自体を完全に体外に排除することは難しいため、再発することがあります。予防策としては、HPVワクチンの接種が効果的で、特に若年層に推奨されています。
日本国内では、性教育の普及とともにHPVワクチンの接種率が徐々に増加しており、尖圭コンジローマの予防意識が高まっています。しかし、依然として性感染症全体の認識が不十分なため、正しい知識の普及と予防の重要性が強調されています。また、感染が確認された場合には早期に適切な治療を受けることが重要です。
患部にイボを形成する尖圭コンジローマの症状
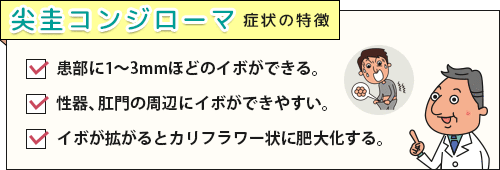
尖圭コンジローマの主な症状として性器に1~3mmほどのイボができます。原因ウイルスであるヒトパピローマウイルスに感染してもすぐに症状は現れません。感染から発症までに早くても数週間、遅くて数ヶ月の潜伏期間があります。
尖圭コンジローマを発症すると性器や肛門などに複数のイボが発生します。このイボはカリフラワーのような形状に肥大化することがあります。イボの色は淡紅色や灰色、もしくは褐色です。時には乳頭状、鶏冠状とも称され、見ただけで尖圭コンジローマとわかる特徴的な形をしています。
尖圭コンジローマによるイボができた際、自覚症状のない方もいれば痛みやかゆみを感じる方もいます。特に女性の場合は膣内壁にイボができることもあります。気づくのが遅れるため、発症に気づかず他人へ感染させてしまうリスクがあります。尖圭コンジローマに気付いたら、必ずパートナーにも検診を受けてもらいましょう。
免疫力の低下しているヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者はイボの生育スピードが速く、治療の難易度も難しくなってしまうことが多くなります。発症したら塗り薬を塗布するなど、すばやく治療にうつることが大切です。
尖圭コンジローマの放置は症状を悪化させて治療を困難にします。
尖圭コンジローマを治療せずに放置した場合、症状が悪化する原因となります。イボの肥大化や増加、病変部の拡大が進行するおそれがあります。尖圭コンジローマは、時間が経つにつれウイルスが増殖・拡散してイボが広がっていきます。個人差があり、中には放置してもイボが増えないケースや無治療でも消失するケースもあります。とは言え、自然治癒する割合は全体の20~30%程度にとどまります。
尖圭コンジローマを放置して症状が進行すると、治療が難しくなっていきます。イボがどんどん大きくなるため、外科手術による切除が必要な場合もあります。切除を行うと、患部に手術痕や術後の疼痛が残って負担となります。初期段階の小さいイボであれば、塗り薬だけで完治させることができます。感染が疑われる際には放置せず、少しでも早く治療を始めましょう。
尖圭コンジローマの見分け方
陰部にイボを形成するのは尖圭コンジローマだけではありません。イボの多くは、治療の必要がない生理現象によるものです。尖圭コンジローマとよく間違えられるイボは、女性の腟前庭乳頭腫症や男性の真珠様陰茎小丘疹・フォアダイスです。いずれも放置しても問題のない無害な生理現象です。
女性の見分け方はイボの規則性です。
女性が間違えやすい腟前庭乳頭腫症では、3~5mm程度の棍棒状のイボが小陰唇の内側に縦向きで並びます。見分け方のポイントは、腟前庭乳頭腫症のイボが左右対称性かつ規則的に並ぶという点です。コンジローマは不揃いに発生しますので、イボに規則性が見られる際には腟前庭乳頭腫症が疑われます。
男性の見分け方はイボの並びや手触りです。
男性が間違えやすい真珠様陰茎小丘疹とフォアダイスはイボというよりブツブツです。大きさの均等がとれた1mm程度のイボが陰茎から環状溝(カリ首)にかけて生じます。見分け方のポイントは、イボの並び方や表面を触った時の感触です。コンジローマのイボは、並びも大きさもまばらで表面がザラザラしています。環状溝に沿って輪を描くような特徴的な並び方であれば真珠様陰茎小丘疹、不揃いだが表面がツルツルとしているようであればフォアダイスが疑われます。
HPVの接触感染が尖圭コンジローマの原因
ヒトパピローマウイルス(HPV)は確認されているだけでも100種類以上あります。ウイルスのタイプによって病状も異なり、低頻度ではありますが癌に発展するウイルスも存在します。
尖圭コンジローマの原因となるHPVは、将来的に癌になる可能性の低い「低リスク型ヒトパピローマウイルス」です。ヒトパピローマウイルスは、基本的に触れることで感染します。
尖圭コンジローマの感染者と性交を行うと、皮膚や粘膜の小さな傷から体内にウイルスが侵入して感染します。3週間~8ヶ月の潜伏期間がありますが、やがて尖圭コンジローマを発症します。HPVは潜伏期間が長いため、どのタイミングで感染したかわかりにくいことが特徴です。一方が感染していれば、その性交のパートナーも高い確率で感染しています。相手に症状がない状態であっても、共に検査・治療を受けることが大切です。
保護者がHPVに感染している場合は、患部の管理が不十分だと幼児に感染して尖圭コンジローマを発症することがあります。また、医療機関での治療の際、医者や看護師などの手や器具を経由してウイルスが感染してしまうケースもあります。
妊婦が尖圭コンジローマにかかった場合、悪化すると出産に支障をきたします。新生児がHPVに感染するのを防止するために帝王切開が選択されることもあります。
尖圭コンジローマは症状によって治療法を選択
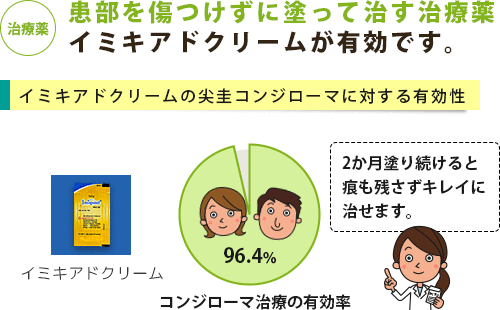
- 尖圭コンジローマの治療に有効な成分
- イミキモド
免疫機能を高める物質の分泌量を増加させます。尖圭コンジローマを治療する効果に優れています。日光角化症にも適応があり、その他の皮膚腫瘍にも有効です。
- イミキモドが配合されている商品
- イミキアドクリーム
患部に直接塗る尖圭コンジローマの治療薬です。コンジローマの症状があらわれている部分に8週間ほど塗布すると、イボやブツブツを改善できます。
尖圭コンジローマは、正しい治療を行えば根治することが可能です。ただし治癒から3ヶ月以内に25%の方が再発をしています。長期間にわたる治療が必要となることもあります。
尖圭コンジローマの治療は、複数の治療法を組み合わせて行うと効果的です。症状の度合いや病変の場所によっても治療法が変わります。軟膏の使用や凍結療法、レーザーによる外科的療法などを行います。免疫力の低下している方は、尖圭コンジローマの治療に時間がかかり再発率も高くなります。特にHIV感染者、妊婦、免疫抑制剤を投与している方は特に注意が必要です。
ヒトパピローマウイルスの増殖を防ぐ塗り薬が有効です。
イミキアドクリームは外性器や肛門周辺のイボへの使用を想定して開発されたコンジローマ治療薬です。
イミキアドクリームには、ヒトパピローマウイルスの増殖を抑える効果があります。1日おきに週3回、患部への塗布を最大16週にわたって行います。薬を患部に塗り込んだら6~10時間後には洗い流しましょう。これは長時間放置することによって皮膚障害が発生する可能性があるためです。
尖圭コンジローマの治療はイボの大きさや数などによって治療法を選択します。外用薬による治療は唯一どのような症状に対しても使用できる尖圭コンジローマの治療法です。
イミキアドクリームは治療後に痕が残りにくいという長所があります。患部をきれいに治せるのが利点です。
手術などで直接イボを切り取る治療方法。
イボの状態によっては跡が残ってしまうこともあり、手術で取り除く場合もあります。
薬物療法以外にも液体窒素を使った凍結療法や電気メスを使った外科的療法があります。
外科的療法ではレーザーや専用器具によるイボの切除をします。ただし、イボを切除してもウイルスが体に残っている可能性があります、これらの治療法はある程度の期間、継続して行うことが大切です。
尖圭コンジローマの予防にはコンドームが有効
尖圭コンジローマの主な感染原因は性行為です。予防には、コンドームの使用が有効です。女性の場合、外陰部に皮膚炎があると感染リスクが強まります。また、患部が広範囲にわたっている場合にも注意が必要です。
ワクチンを接種することでもヒトパピローマウイルスの感染を防ぐことができます。1回の投与ではHPVに対する抗体が十分ではありませんので、半年で3回のワクチン摂取が必要となります。ワクチンの効果は少なくとも8年は持続することが確認されています。
ワクチンには病気の症状を抑える働きはありませんので、ウイルスの感染予防のみ有効です。すでに症状がでている場合には、治療が必要となります。
![[204時間限定] 夏のタイムセール](/template/default/img/campaign/20250723/bn-campaign-a-20250723.webp)