副鼻腔炎(蓄膿症)がよくわかる疾患ガイドページ
副鼻腔炎は、鼻と顔の周囲に位置する副鼻腔の粘膜が炎症を起こす疾患です。この炎症は、感染、アレルギー反応、あるいはその他の要因によって引き起こされることがあります。典型的な症状には、鼻詰まり、顔の痛みや圧迫感、黄色や緑色の鼻水、嗅覚の低下が含まれます。副鼻腔炎は急性と慢性の二つの形態があり、適切な治療を行うことで症状は大きく改善可能です。
このガイドでは、副鼻腔炎の原因、症状の識別、効果的な治療法、そして疾患の予防に向けたアドバイスを患者に提供し、快適な呼吸への道を支援します。
副鼻腔炎(ふくびくうえん)とは?

副鼻腔炎は、顔の周りにある空洞、副鼻腔の内側の膜が炎症を起こす疾患です。これは、風邪のウイルス、アレルギー、時には細菌の感染などによって引き起こされます。症状には、鼻詰まり、黄色や緑色の鼻水、顔の痛みや重み、嗅覚の低下などがあります。炎症が慢性化すると、蓄膿症(ちくのうしょう)とも呼ばれる状態になり、副鼻腔内に膿が溜まりやすくなります。
日本では、季節の変わり目や花粉症の季節に副鼻腔炎の患者が増える傾向にあります。特に都市部では、空気汚染や室内環境が原因で一年中症状を訴える人が少なくありません。また、蓄膿症は副鼻腔炎が悪化すると発生することが多く、慢性化すると繰り返し症状が現れるため、日常生活に影響を及ぼすこともあります。
治療は原因に応じて変わりますが、通常は抗生物質、抗アレルギー薬、ステロイド含有の鼻スプレーなどが用いられます。重症の場合や慢性化している場合には、外科的な処置が必要になることもあります。副鼻腔炎と蓄膿症を防ぐためには、早期に適切な治療を受け、可能であれば原因となるアレルゲンや刺激物を避けることが大切です。定期的な健康チェックと、症状が出たときの早めの受診を心がけましょう。
黄色い鼻水、鼻づまり、頭痛などが副鼻腔炎の主な症状
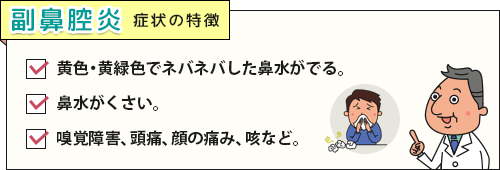
| 自覚症状 | 悪臭を伴う黄色くて粘り気のある鼻水、鼻づまり、嗅覚障害、頭痛、顔の痛み、咳など。 |
|---|---|
| 発症の条件 | 以下の要素に当てはまる時期に発症しやすい。 ・風邪が長引いたとき ・虫歯を放置しているとき ・花粉症が酷いとき |
| 間違えやすい疾患 | アレルギー性鼻炎(サラサラとした水っぽい鼻水が流れます) |
副鼻腔炎では、粘り気のある鼻水や鼻づまり、匂いが分からない、咳、頭痛、喉の痛みなどの不快な症状がみられます。鼻水はネバネバとした粘性であり、黄色または黄緑色をしています。悪臭を伴っているため、鼻水そのものが口臭の原因となることもあります。
後鼻漏(喉に流れ落ちる鼻水のこと)になると喉の表面に鼻水が張り付いて、咳や喉の違和感、痰がらみの原因となります。咳が止まらないといった症状は、夜間よりも昼間に増悪する方が多いです。後鼻漏の傾向が強い方では、鼻から鼻水がでないこともあります。
症状の出始めである急性期の副鼻腔炎では、頭全体や後頭部などに頭痛がみられます。頭痛は、下を向いた際に強くなるのが特徴です。
頭痛と共に、顔の痛みも副鼻腔炎の症状として現れます。頬骨や目の奥、鼻の付け根など副鼻腔がある部位に圧迫感を伴う痛みが生じます。顔の痛みは、口を開けたり物を咀嚼したりなど、顔を動かした際に感じることが多いです。痛みのある部位に腫れが生じることもあります。歯の根元に炎症が及んでいる場合、歯痛が起きることもあります。歯痛の原因が副鼻腔炎である場合、上顎の奥歯に痛みの症状が現れます。
副鼻腔炎は風邪に伴って発症するケースが多いのですが、発熱の症状がみられることはあまりありません。発熱や節々の痛みなどの症状が繰り返し見られる場合には、喉や耳に炎症が拡がっている可能性があります。特に激しい頭痛や吐き気が見られる場合には、髄膜炎を合併しているおそれがありますので注意が必要です。
慢性化すると鼻づまりの症状が数ヶ月間つづきます。
副鼻腔炎の症状がいつまで経っても治らない場合には、慢性化している可能性があります。
鼻水や鼻づまりなどの症状が3ヶ月以上続くものは、慢性副鼻腔炎と呼ばれます。鼻がつまって匂いがわからない、眠れないといった状態が長期的に続くため、日常生活に大きな支障がでます。口呼吸が増えることで口臭に悩む方もいます。慢性副鼻腔炎では、頭重感や倦怠感などの随伴症状もみられます。頭痛や顔の痛みはほとんどみられません。
慢性副鼻腔炎になると、鼻茸(はなたけ)と呼ばれるポリープが鼻腔内にできることがあります。鼻茸は、鼻腔内を塞いで鼻づまりを悪化させます。鼻茸のサイズが大きい場合は、手術による切除が必要となります。
副鼻腔炎の原因は風邪などによる炎症や膿の貯留(蓄膿)
副鼻腔炎の主な発症のきっかけは、風邪による副鼻腔の炎症です。風邪に伴うウイルスや細菌などの病原体の感染により、副鼻腔に炎症が生じることで、膿を含んだ鼻水などが症状として現れます。炎症のみを起因とする発症の初期段階は、急性期と呼ばれます。急性副鼻腔炎の状態であれば、比較的治療は簡単であり、1ヶ月以内の治癒が見込めます。
厄介なのは、膿が持続的に溜まった状態になる慢性副鼻腔炎です。慢性副鼻腔炎は、粘膜の炎症が長期化した場合に発症します。粘膜が腫れて鼻腔への通り道を塞いだり、膿を排出する粘膜の働きが低下したりすることで、副鼻腔の中に膿が溜まってしまいます。排出されない膿が炎症を悪化させて、さらに膿が溜まるといった悪循環に陥った状態が慢性副鼻腔炎です。慢性副鼻腔炎は治りにくく、症状が3ヶ月以上続きます。
風邪以外にも虫歯、鼻炎などが副鼻腔炎の原因となります。
- 真菌(カビ)
- 虫歯・歯周病
- アレルギー性鼻炎
- 鼻中隔が曲がってる
- 好酸球
副鼻腔炎は風邪の悪化に伴う発病が大半ですが、副鼻腔に炎症を起こすのはウイルスや細菌だけではありません。再発を防止するうえでも、自身が副鼻腔炎に罹患した原因を把握しておくことが大切です。特に好酸球や真菌によっておきる副鼻腔炎は、通常では有効となる抗生物質が効きません。内視鏡手術による患部の切除が必要となります。
真菌(カビ)が鼻に入り込む副鼻腔真菌症
真菌というカビの仲間が鼻に入り込むことで、副鼻腔炎が生じることがあります。副鼻腔真菌症とも呼ばれます。もともと風邪を引いていて、鼻粘膜の洗浄機能が低下しているタイミングに真菌感染が起こりやすいです。またカビに対するアレルギーを有する方でも発症しやすいとされています。
虫歯・歯周病の炎症が上顎洞にまで広がる
虫歯や歯周病を放置していると、副鼻腔炎が生じることがあります。鼻の横あたりにある上顎洞という名前の副鼻腔は、歯の根元のすぐ近くに位置しています。虫歯や歯周病の炎症が上顎洞にまで広がることで副鼻腔炎を発症します。
アレルギー性鼻炎による鼻粘膜の炎症
花粉症などのアレルギー性鼻炎をきっかけに副鼻腔炎を発症することもあります。実際にアレルギー性鼻炎患者の約4割が副鼻腔炎を併発しているとの報告もあります。風邪の時と同様に、鼻粘膜の炎症が副鼻腔に及んだ場合に発症します。花粉以外にも、アレルゲンにはダニやホコリなどのハウスダストが含まれます。
鼻中隔が曲がってる(鼻中隔湾曲症)
鼻中隔(びちゅうかく)とは、鼻を左右に隔てている仕切りの壁のことです。生まれつき鼻中隔が曲がっていると、片側の鼻の通りが悪くなって副鼻腔炎を生じやすくなります。子供の頃は鼻中隔が真っ直ぐだった方でも、成長に伴って曲がることも多く、大人になってから副鼻腔炎を発病することもあります。
好酸球の過剰な活性化
好酸球とは、血中にある白血球の一種です。好酸球の過剰な活性化によって副鼻腔炎が発症しますが、なぜ好酸球が活性化するのかについては不明です。鼻腔内にポリープが多発します。好酸球による副鼻腔炎は非常に厄介であり、手術で病変を取り除いてもすぐに再発する難治性の病気です。
副鼻腔炎の治療には細菌と炎症を抑える抗生物質が有効
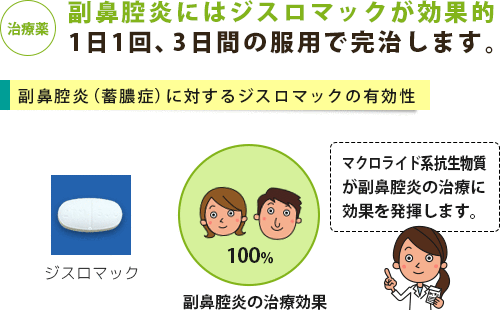
- 副鼻腔炎の治療に有効な成分
- アジスロマイシン
クラミジアや歯周病といった細菌性の感染症に有効なマクロライド系の抗生物質です。呼吸器感染症、耳鼻科領域感染症、歯科・口腔外科領域感染症などに効果を発揮します。 - クラリスロマイシン
タンパク質の合成を妨害して細菌の繁殖を抑えるニューマクロライド系の抗生物質です。クラミジア、呼吸器、泌尿器などの細菌感染症に効力を示します。 - レボフロキサシン
細菌感染症に有効なニューキノロン系の合成抗菌薬です。さまざまな細菌・ウイルスの感染症に有効で、クラミジア、副鼻腔炎、肺炎、胃腸炎、結核など幅広い治療に用いられます。
- アジスロマイシンが配合されている商品
- ジスロマック
アジスロマイシンを有効成分としたマクロライド系抗生物質の先発品です。1回の服用で10日間も効果が持続する特性を活かした効果的な治療が可能で、クラミジア改善率90.7%とされています。 - クラリスロマイシンが配合されている商品
- ゾクラー
クラリスおよびクラリシッドと同じクラリスロマイシンを有効成分としたジェネリックです。性器クラミジア感染症に伴う尿道炎、子宮頸管炎、など、様々な用途で使われます。 - レボフロキサシンが配合されている商品
- レボクイン
ニューキノロン系の抗菌薬クラビットのジェネリックです。クラミジア属の細菌だけでなく尿道炎や子宮頸管炎を始めとした40種類以上もの細菌性疾患への適応があります。
| 治療法の内容 | 抗生物質の投与もしくは膿の吸引 |
|---|---|
| 診察が行える診療科 | 耳鼻科 |
| 施術に使用する薬または器具 | マクロライド系抗生物質 吸引器 |
副鼻腔炎の治療では、抗生物質の投与や患部に溜まった膿の吸引が行われます。抗生物質で炎症を悪化させる細菌を除菌しつつ、吸引器で副鼻腔の蓄膿や鼻水を吸い出すことで治癒が早まります。抗生物質は内服が基本ですが、薬を霧状にして粘膜に直接当てるネブライザーという機械が使われることもあります。
副鼻腔炎に効果が高いのは、マクロライド系の抗生物質です。マクロライド系には、殺菌効果に加えて、鼻粘膜の炎症を抑える効果もあります。代表的なマクロライドとしては、アジスロマイシンやクラリスロマイシンが挙げられます。
重症化した副鼻腔炎には手術が必要なこともあります。
抗生物質や吸引を行っても症状が改善されない場合、内視鏡手術が必要となることもあります。鼻から内視鏡を入れて、モニター画面を見ながら鼻粘膜にある鼻茸(ポリープ)を切除する手術です。鼻腔を塞いでいた鼻茸が除去されることで、鼻の通りが改善されます。副鼻腔炎の内視鏡手術は出血や痛みもなく、後遺症の心配もありません。
副鼻腔炎の予防で大切なのは風邪を長引かせないこと
副鼻腔炎は、風邪をきっかけに罹ることが多い疾病です。特に風邪で鼻粘膜の炎症が長引くと、副鼻腔炎が慢性化するおそれがあります。風邪をひいた際には、出来るだけ早く治すことが大切です。よく休息をとり、バランスの良い食事を摂取して治療に専念することを心がけましょう。
特に鼻づまりの症状が酷い鼻風邪には要注意です。鼻うがいを1日1〜2回ほど行い、鼻の中を清潔に保ちましょう。鼻うがいには、ぬるま湯に塩を溶かした生理食塩水を使ってください。鼻づまりが続くようであれば、耳鼻科を受診して副鼻腔洗浄をしてもらいましょう。
アルコールは、血行を良くして鼻づまりを悪化させるおそれがあります。風邪を引いた時には、飲酒を控えてください。
![[204時間限定] 夏のタイムセール](/template/default/img/campaign/20250723/bn-campaign-a-20250723.webp)