バナナは1日2本まで!食べ過ぎによる下痢・カリウム過剰などの健康リスク
- 公開日
- 2025年08月14日
- 更新日
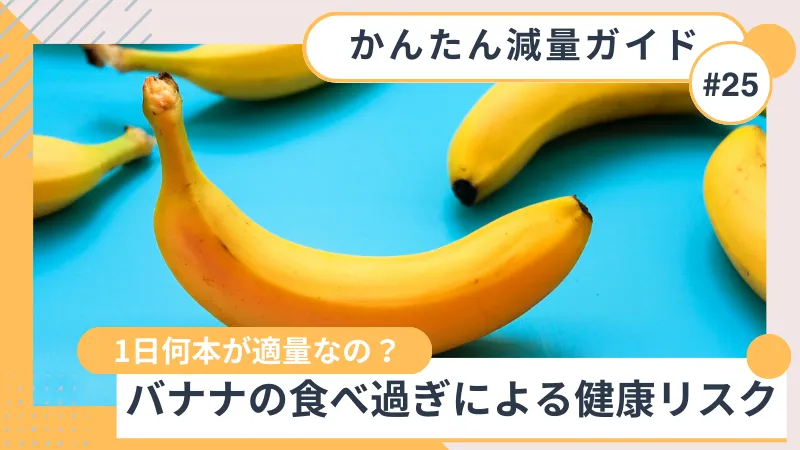
「健康のために毎日バナナを食べている」という方は少なくありません。甘くて手軽に食べられるうえ、栄養価も高いため、朝食や間食に取り入れている方も多いでしょう。
しかし、バナナのように栄養豊富な食品でも、摂りすぎれば健康に悪影響を及ぼすことがあります。
この記事では、バナナを食べ過ぎた場合に起こりうる健康への影響をわかりやすく解説します。あわせて、1日の適量やバナナに含まれる主な栄養素についても紹介します。
食べ過ぎによる弊害を理解し、安全で効果的にバナナを楽しむためのポイントをぜひ最後までチェックしてください。

バナナダイエットは痩せる?効果的な方法やSNSの口コミを紹介
バナナがダイエットに役立つ5つの理由や、朝または夜にバナナを食べる減量方法を紹介。バナナをダイエットに用いる際の注意点まで徹底解説。
下痢やカリウム過剰などバナナの食べ過ぎでおきる5つの健康リスク

バナナは健康によい果物として知られていますが、食べ過ぎると栄養バランスが崩れ、体調不良の原因になることがあります。
バナナの食べ過ぎによって起こり得る主なリスクには、以下のようなものがあります。
これらのリスクについて、順番に解説します。
カロリー過多で太る原因になる
バナナは腹持ちがよく栄養価も高いため、ダイエット中のおやつとしても人気があります。ただし、果物の中ではカロリーが比較的高いため、食べ過ぎには注意が必要です。
バナナは100gあたり約93kcalあり、他の果物と比べても高めの数値です。以下に代表的な果物のカロリーを高い順にまとめました(食品成分データベース,文部科学省,[リンク])。
| 果物名 | カロリー(kcal) |
|---|---|
| バナナ | 93 |
| マンゴー | 68 |
| ぶどう(皮なし) | 58 |
| りんご(皮なし) | 53 |
| 桃(白肉種) | 38 |
表を見て分かるように、バナナ(93kcal)は桃(38kcal)の約2.4倍のカロリーがあります。果物というと「ヘルシーでカロリーが低い」というイメージを持たれがちですが、種類によってはここまで違いがあるのです。
人の体は、摂取カロリーが消費カロリーを上回ると、余った分を脂肪として蓄える性質があります。
つまり、健康的なイメージのあるバナナでも、1日に何本も食べれば気づかないうちにカロリーオーバーとなってしまうのです。

痩せる薬の通販ランキング【内科でもらえるダイエット薬】最新版
食事を我慢できない人や、運動をしたくない人におすすめの痩せる薬を紹介します。肥満外来で処方されている病院の薬の種類や通販人気ランキングが分かります。
栄養バランスが偏る
バナナは手軽に食べられ、カリウムなどを豊富に含む栄養価の高い果物です。ただし、バナナばかりを食べていると、栄養バランスが崩れてしまう可能性があります。
実際に、バナナ100gあたりに含まれる主な栄養素は以下のとおりです(食品成分データベース,文部科学省,[リンク])。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 1日の摂取目標量の目安(成人) | 1日摂取目標量に対する割合 |
|---|---|---|---|
| カリウム | 360mg | 2,600~3,000mg | 約12~14% |
| 炭水化物 | 22.5g | 250~325g*1 | 約7~9% |
| 食物繊維 | 1.1g | 18~22g | 約5~6% |
| タンパク質 | 1.1g | 50~65g | 約1.7~2.2% |
| 脂質 | 0.2g | 44~67g*2 | 約0.3~0.5% |
| カルシウム | 6mg | 650~800mg | 約0.8~0.9% |
※1:総エネルギー摂取量の50~65%(2,000kcalで換算)
※2:総エネルギー摂取量の20~30%(2,000kcalで換算)
この表から分かるように、バナナは炭水化物やカリウムに優れていますが、タンパク質や脂質、カルシウムといった栄養素はごくわずかしか含まれていません。
そのため、バナナばかりを食べ続けると、他の重要な栄養素が不足し、かえって健康を損なう可能性があります。
バナナはあくまでも食事の一部として取り入れ、タンパク質が豊富なヨーグルトや牛乳、ビタミンやミネラルが豊富な他の野菜や果物など、様々な食品と組み合わせて栄養バランスを整えることが大切です。
下痢やお腹の不調が起きる
バナナを食べ過ぎると、下痢を引き起こすことがあります。主な原因は、バナナに含まれる食物繊維とオリゴ糖の働きです。
バナナには、水に溶けて便を柔らかくする水溶性食物繊維と、便のかさを増やして腸のぜん動運動(便を押し出す動き)を促す不溶性食物繊維の両方が含まれます。適量なら便通を整える効果がありますが、摂りすぎると腸への刺激や水分量が過剰となり、便が緩くなることがあります。
さらに、バナナに含まれるフラクトオリゴ糖は、善玉菌のエサとなり腸内環境を改善しますが、一度に大量に摂ると腸内でガスが発生しやすくなり、体質によっては下痢を招く場合があります。
こうした作用が重なり、腸の動きが活発になりすぎたり水分の再吸収が追いつかなくなったりすることで下痢が起こります。特に消化機能が未熟な子どもや消化力が低下している高齢者、あるいは過敏性腸症候群(IBS)など腸が敏感な人では、影響が出やすいため注意が必要です。
結石になりやすい人は注意が必要
バナナは栄養価の高い果物で、微量ながらシュウ酸(しゅうさん)という成分を含んでいます。シュウ酸は尿中でカルシウムと結合して結晶をつくり、それが蓄積すると「結石」と呼ばれる固まりになることがあります。
尿中のカルシウムやシュウ酸などが結晶化し、石のような固まりになったものです。小さいものは自然に排出されますが、大きくなると腎臓や尿管に詰まり、強い痛みや排尿障害を引き起こします。
バナナは一般的に低シュウ酸食品とされており、健康な方が1~2本程度を食べる場合、シュウ酸による結石リスクが高まる可能性は低いと考えられます。
ただし、結石を繰り返している方や尿検査で高シュウ酸尿と指摘された方は注意が必要です。1日3本以上を長期間にわたって食べ続けるなど過度な摂取に加え、水分不足や高塩分食、ほうれん草やナッツなど他の高シュウ酸食品との組み合わせが重なると、結石のリスクが高まる可能性があります。
腎臓が弱い人はカリウムの摂りすぎに注意
バナナはカリウムを豊富に含む果物で、100gあたり約360mgものカリウムが含まれています。
カリウムは、体内の塩分バランスを整える大切なミネラルですが、腎機能が低下している方が過剰に摂取すると、「高カリウム血症」を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
本来、尿として排出されるはずのカリウムが、腎機能の低下などによって体内にたまり、血液中の濃度が異常に高くなった状態です。軽い場合は症状がないこともありますが、進行すると吐き気、しびれ、不整脈などを起こし、重症では心停止に至ることもあります。
腎臓に不安がある方、とくに慢性腎臓病(CKD)や透析治療中の方は注意が必要です。さらに、高血圧や心臓病の治療で使われる一部の薬(降圧薬や利尿薬など)や、カリウムを多く含む減塩タイプの塩を使用している場合も、体内のカリウムが増えやすくなります。こうした方は、バナナの摂取量について必ず医師や管理栄養士に相談し、指示に従いましょう。
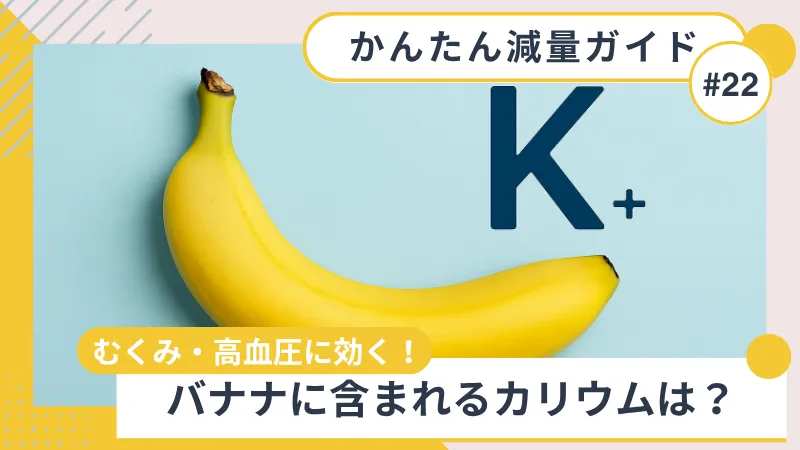
バナナはカリウムが豊富!むくみ・血圧への効果や1日何本食べるべき?など解説
バナナはカリウムが豊富な果物!バナナに含まれるカリウムの含有量や、血圧の改善・むくみの解消といったカリウムの効果、過剰摂取・不足によるリスクについて解説。
3本は食べ過ぎ!?バナナの適量は1日1~2本

バナナの食べ過ぎがさまざまな健康リスクを招くことはすでに説明しましたが、では具体的に「何本からが食べ過ぎ」なのでしょうか?
健康に良いとされるバナナですが、1日に3本以上食べるのは過剰摂取にあたるといえます。
農林水産省の「食事バランスガイド」によると、1日に摂取する果物の適量は約200gとされています(1日分の適量について, 食事バランスガイド,農林水産省, [リンク])。
一般的なバナナの可食部は、1本あたり100g前後(80~120g)であることから、1日1~2本程度が適量と考えられます。
それ以上の摂取は、糖質やカロリーの過剰摂取につながるおそれがあるため、特に健康管理やダイエットを意識している方は注意が必要です。
食べ過ぎによる弊害を避けるためにも、バナナを食べる際は適量を守りましょう。
適量を守ればバナナは健康的な果物

バナナは食べ過ぎると健康への悪影響が懸念されますが、1日1~2本の適量を守ればとても健康的な果物です。
バナナには、ブドウ糖や果糖が豊富に含まれており、体内ですばやくエネルギーに変わります。そのため、エネルギー補給として朝食や運動の前後に食べるのにぴったりです。
特に、脳のエネルギー源として重要なブドウ糖を効率よく補えるため、集中力を保ちたいときや、疲れを感じたときにも役立ちます。
また、カリウムが豊富に含まれているのもバナナの魅力のひとつです。カリウムは余分な塩分を排出する働きがあり、血圧の安定やむくみの改善が期待できます。
さらに、バナナには食物繊維も含まれており、便通を改善して腸内環境を整えるうえでも効果的です。
このように、バナナは適量を守って上手に取り入れることで、毎日の健康をサポートしてくれる頼もしい果物です。
食べ過ぎた次の日にはバナナがおすすめ
前日の夜に外食やお酒、スイーツなどをたくさん食べて「ちょっと食べ過ぎたかも…」と感じた翌日の食事には、バナナがおすすめです。
食べ過ぎた翌日は、摂取カロリーを控えめにしつつ、消化が良く、体内の余分な塩分を排出してくれる栄養素を含む食事が理想とされています。
バナナはこの条件をすべて満たしており、まさにリセット食にぴったりの果物です。
バナナに豊富に含まれるカリウムには、前日に摂り過ぎた塩分を体外へ排出する働きがあり、むくみの解消につながります。
また、バナナの食物繊維が腸の動きを整えて便通を促し、食べ過ぎで疲れた胃腸をやさしくサポートしてくれます。
そのまま食べるのはもちろん、ヨーグルトに入れたり、牛乳と一緒にスムージーにしたりすることで、満足感も得られつつ整腸効果も期待できる朝食になります。
胃腸をいたわりながら、翌日を軽やかにスタートしたいときは、ぜひバナナを取り入れてみてください。
バナナの食べ過ぎに関するQ&A
-
- バナナの食べ過ぎで体臭がひどくなることはある?
- バナナの食べ過ぎが直接的に体臭を強めるという科学的な根拠はありません。食事由来の体臭は、主に脂質やタンパク質を過剰に摂取した場合に強くなる傾向があります。脂質を多く摂ると皮脂の分泌量が増え、それが酸化することで特有のにおいが生じます。また、タンパク質の過剰摂取は腸内の悪玉菌を増やし、アンモニアなどのにおいの強い物質が発生しやすくなります。一方、バナナは脂質・タンパク質の含有量が少なく、一般的に体臭の原因となる物質を多く含む食品ではありません。そのため、健康な人が適量以上に食べたとしても、体臭が顕著に強まる可能性は低いと考えられます。
-
- バナナの食べ過ぎで死亡した例はある?
- 健康な腎臓を持つ人がバナナを食べ過ぎても、命に関わるような事態になるのは極めて稀です。バナナにはカリウムが多く含まれますが、通常は腎臓が余分なカリウムを尿として排出するため、多少多く食べても問題ありません。ただし、腎臓の機能が低下している場合や、カリウムを保持するタイプの降圧薬を服用している場合、また「減塩しお」などのカリウムを使った塩の代替品を多用している場合は、例外的にリスクが高まります。こうした状況では、体内のカリウムが過剰になり「高カリウム血症」と呼ばれる状態を引き起こすことがあり、不整脈や心停止の危険性があります。腎疾患のある方や、医師からカリウム制限を指示されている方は、バナナの摂取量に注意してください。
-
- 赤ちゃんにとってのバナナの食べ過ぎの基準は?
- 1歳半~2歳の子どもは果物全体で1日およそ100g、3~5歳は150gが目安とされています(4つの食品群の年齢別・性別・身体活動レベル別食品構成,[リンク])。これはバナナだけでなく、すべての果物を合わせた量です。バナナに置き換える場合は、そのうち1/2本~1本程度が目安になります。バナナは甘くて食べやすいため、つい多めに与えたくなりますが、食べ過ぎると栄養が偏る原因になることもあります。また、まれにアレルギーを引き起こすことがあるため、特に初めて与えるときは、体調や便の様子を見ながら、少量ずつ試すようにしましょう。子どもの年齢や食事全体のバランスに配慮して、適量を守ることが大切です。
-
- 犬もバナナの食べ過ぎに注意すべき?
- バナナは犬にとって安全な果物ですが、与えすぎると消化不良や便秘、腸閉塞などのリスクがあります。おやつは総カロリーの10%以内に収めるという獣医や動物保護団体の一般的な基準に従い、体重や健康状態に応じて量を調整してください(Can Dogs Eat Bananas?, PetMD, [リンク])。肥満や糖尿病、腎臓病などの基礎疾患がある場合は、必ず獣医師に相談してから与えましょう。バナナは皮を与えず、必ず小さく切って食べやすくしてから与えると安全です。あくまでおやつとして少量を与え、主食の代わりにはしないようにしてください。
食べ過ぎに注意して上手にバナナを取り入れよう

バナナは、カリウムやビタミンB6、食物繊維などをバランスよく含み、手軽に栄養補給ができる身近で便利な果物です。ただし、体によいからといって食べ過ぎには注意が必要です。
バナナを過剰に摂取すると、カロリーや糖分の摂り過ぎによる栄養の偏り、さらには結石や高カリウム血症などの健康リスクにつながるおそれがあります。特に腎臓に疾患がある方や、食生活が偏りがちな方は気をつけましょう。
バナナの適量は、1日1~2本が目安とされています。それ以上食べると、気づかないうちに体に負担をかけてしまう可能性があります。
バナナは、適量を守って上手に活用すれば、健康的な食生活の強い味方になります。無理なく日々の食事に取り入れて、バナナの恵みを正しく活かしていきましょう。

バナナで血糖値は上がる?下がる?スパイクを防ぐ食べ方や注意点を解説
バナナは血糖値の上昇が比較的ゆるやかな「低GI食品」のひとつ。それだけでなく、最新の研究では朝に食べることで、その日1日の血糖値スパイクを抑えるという、驚くべき効果も示唆されています。
